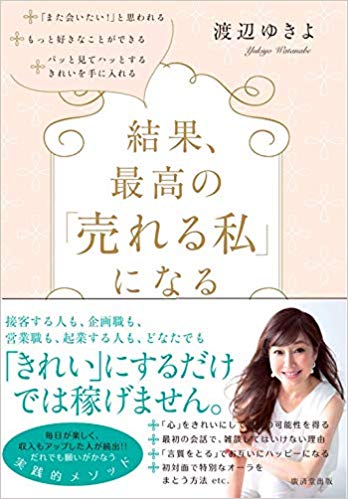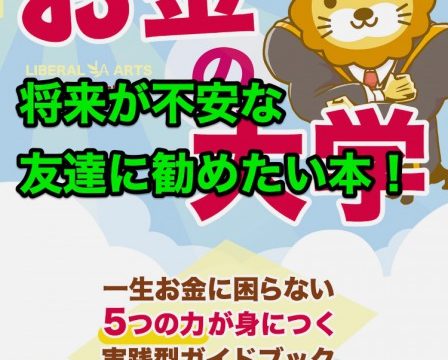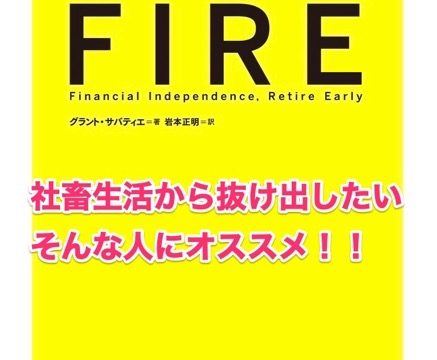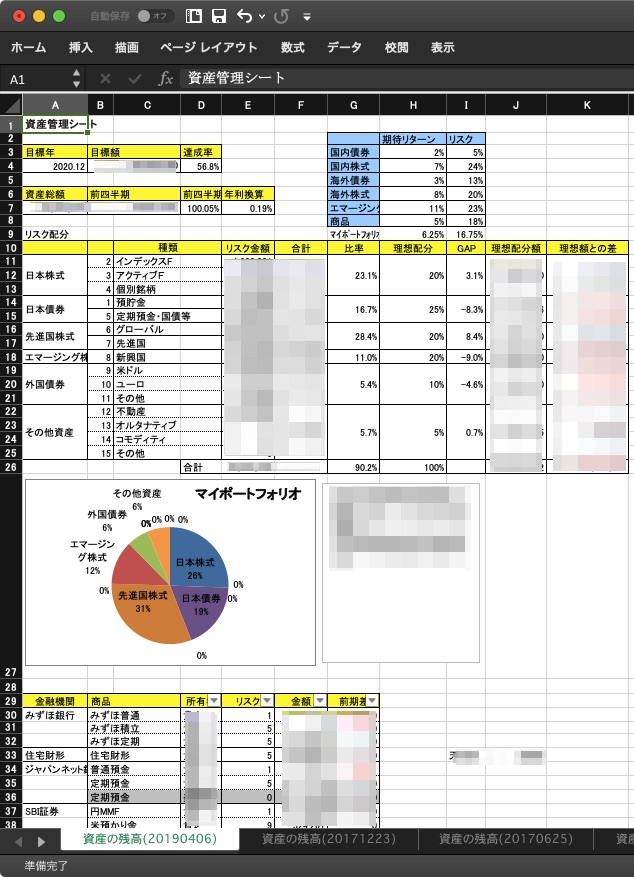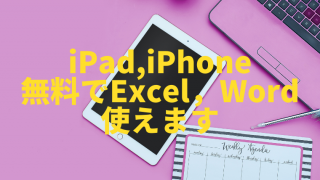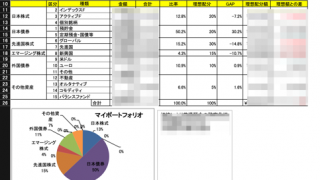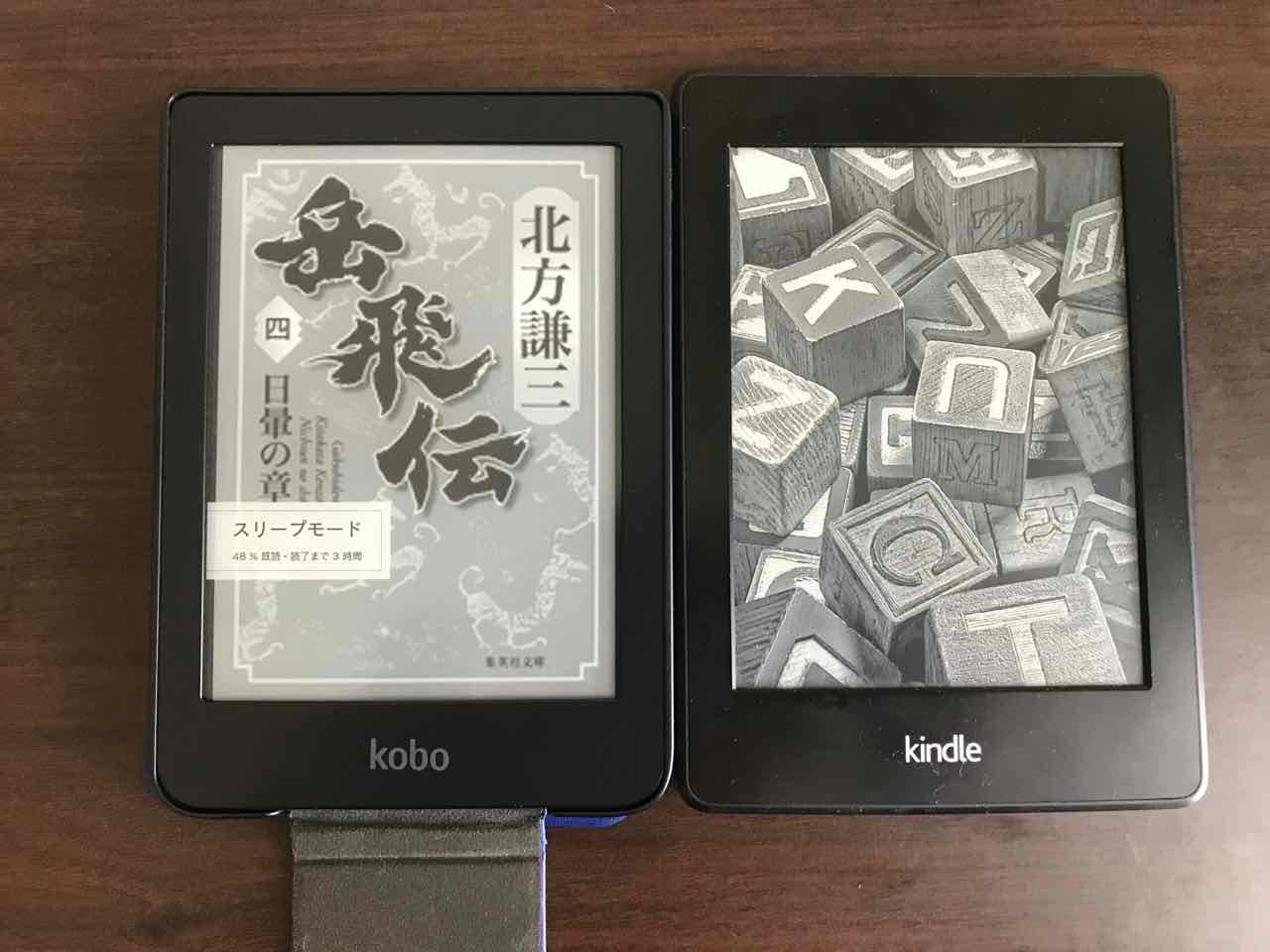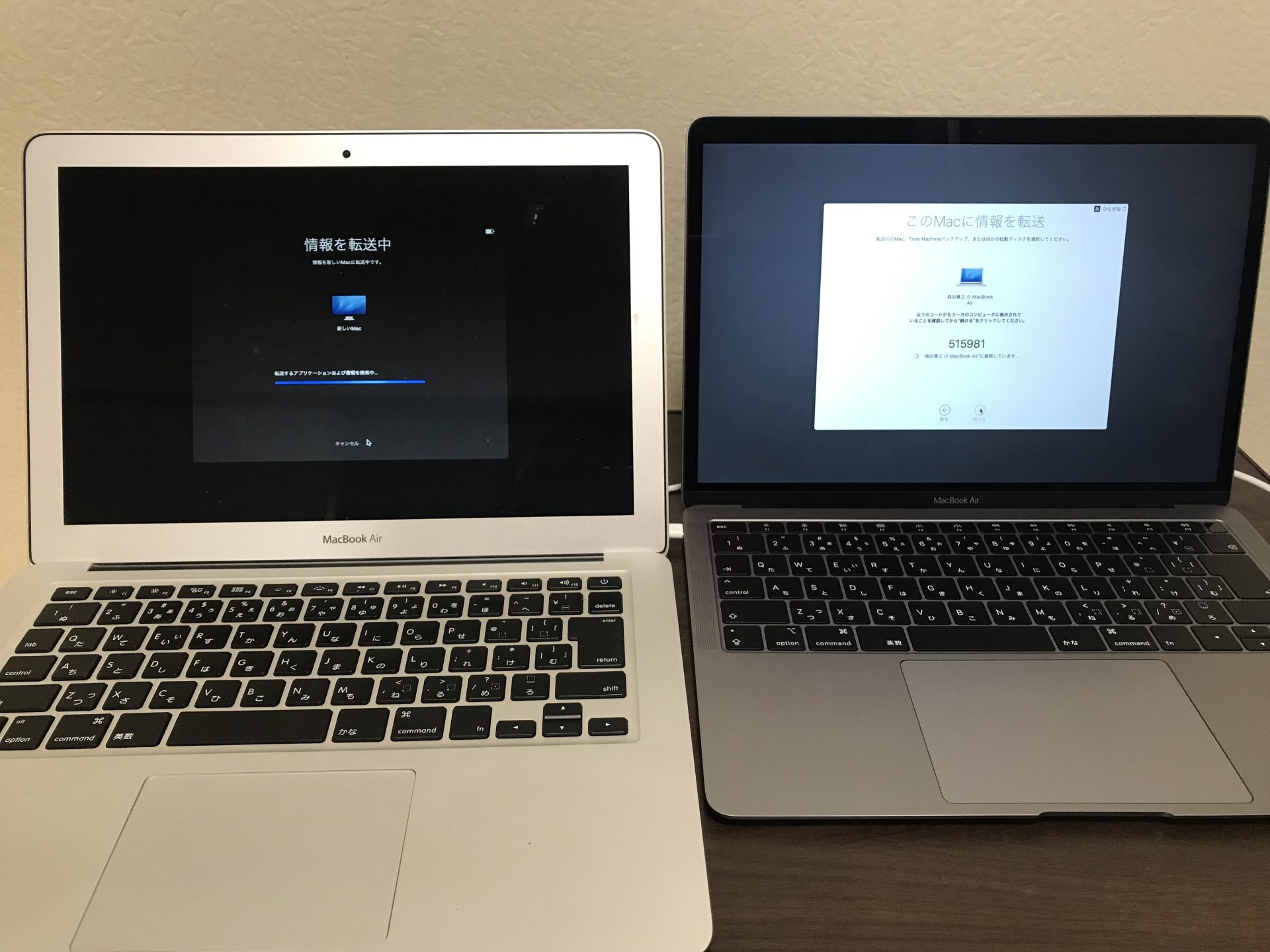学びと投資で豊かになるブログ。今回は学び。
FIREでアーリーリタイヤ後にやりたいと思っている「農業」について”「農業」という生き方 ど素人からの就農入門”という本を読んで考えてみました。
「農」のあるライフスタイルを考える
安曇野の休耕地に悩む
コロナ禍で安曇野の田舎にも自由に帰れなくなってしまった2021年。相続で所有した安曇野の農地の手入れをすることもできません。完全な休耕地。8月にちょっとだけ安曇野に帰ったら、見事に雑草茂る荒れ野原になってしまいました。

近隣に迷惑かけているだろうなと思いつつ、帰れないからそのままです。そして帰れないと思うと、「農のある暮らし」への憧れが強くなってきます。FIREしたら「仕事しての農業」は無理でも「自給的農業」を考えるようになりました。そこで勉強のため、農業の本を手にとってみました。「農業」という生き方 ど素人からの就農入門”。新規就農者たちへのルポタージュです。
「農業」という生き方 ど素人からの就農入門
新規就農者たちへのルポタージュということで、実際に新規就農で苦労した人のいろいろな声が聞けます。
独立までのパターンとして3つ。
・「農家」で研修する
・「研修施設」で研修
・「農業生産法人」で修行し独立
自治体の支援制度が充実しているところもあるということで、安曇野市のサイトは確認しました。
農業スタイルとして紹介されていたのは以下の点。
・味で勝負
・JAとうまくつきあっていく
・有機栽培を突き詰める
・インターネット直販
・少量多品目で勝負する
・企業のなかで農業の可能性を追求する
農業で食べていく覚悟はないですが、社会との接点は「農」でも持ちたい。少量多品目の栽培ができて、大事な人たちに食べてもらえるようになれればと考えるようになりました。
その他、新規就農者の視点でみた「日本の農業の実情」がルポされています。この本で何度もでてくるのは、新規就農者が「農地を借りるのが難しい」ということ。休耕地は大量にあるのに、これを買うことができない、農家が手放さない、制度的に売買が容易でない、という現実があります。ようやく購入した畑と畑が1時間以上離れているという事例もありました。
ここで思うのは私が相続で農地を手にしたのは有り難いことだなということ。家が兼業だけど農家だったので、まったく農業というものを知らないわけでないのも、少しですがアドバンテージだなとも思います。
さいごに
アーリーリタイヤ後の生活像に「農」を意識するようになって、二番目に手にした本です。(最初に手にした本は「ビジネスパーソンの新・兼業農家論」でこちらも刺激的でした)
農業は楽でないとなんとなく分かっているけど、やはりそうなんだなぁということを確認。やはり新規就農者の参入障壁は高いですね。なりわいとして農業一本でやっているのは相当な覚悟が要ります。その点が分かった。ただもちろん大変なだけでなく、もちろん希望も語られてます。
このコロナ禍で農産物や畜産物が出荷できず、生産者が大ダメージを受けているニュースも耳に届いています。この本は2015年の出版ですが、この本に登場した皆さんは大丈夫かなと、余計なお世話ですが最後にそんなことが心配になってしまいました。