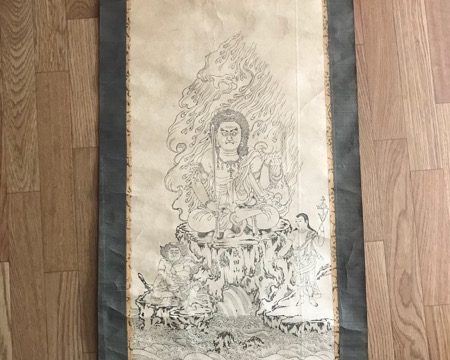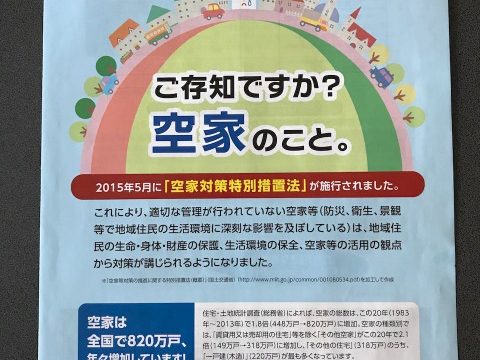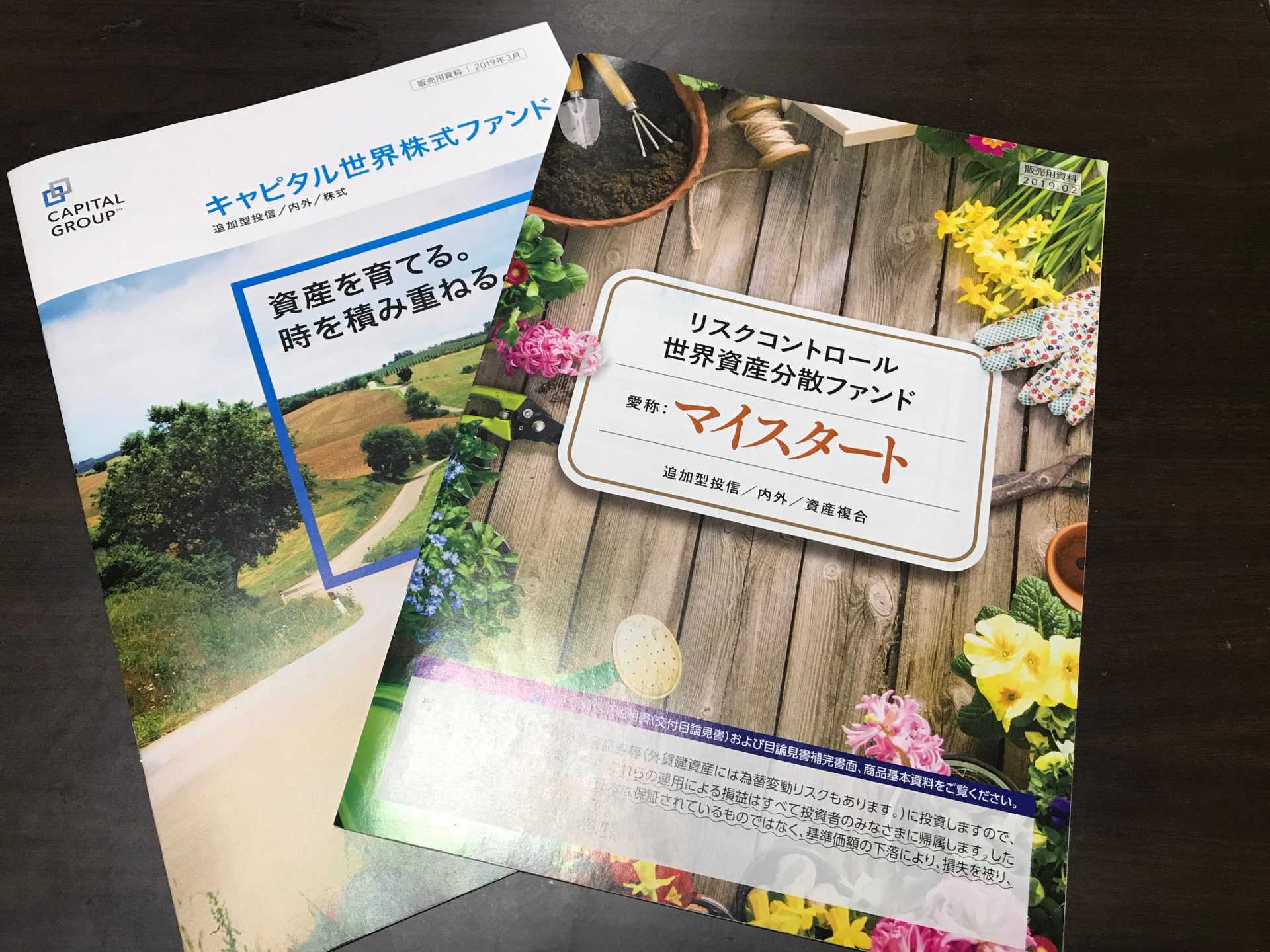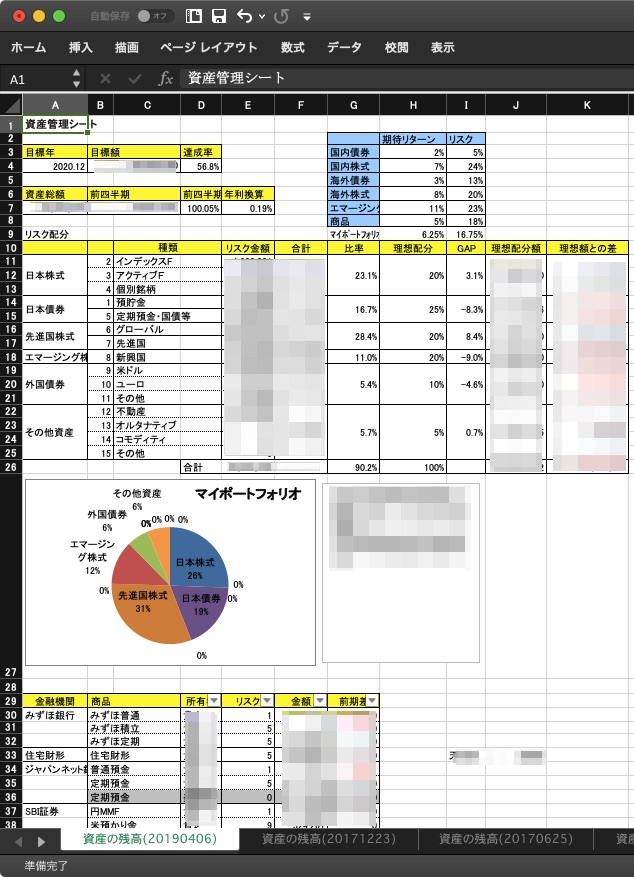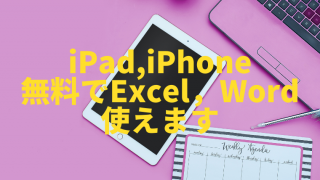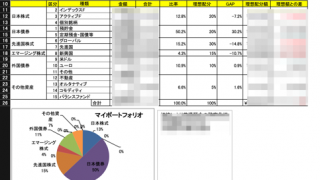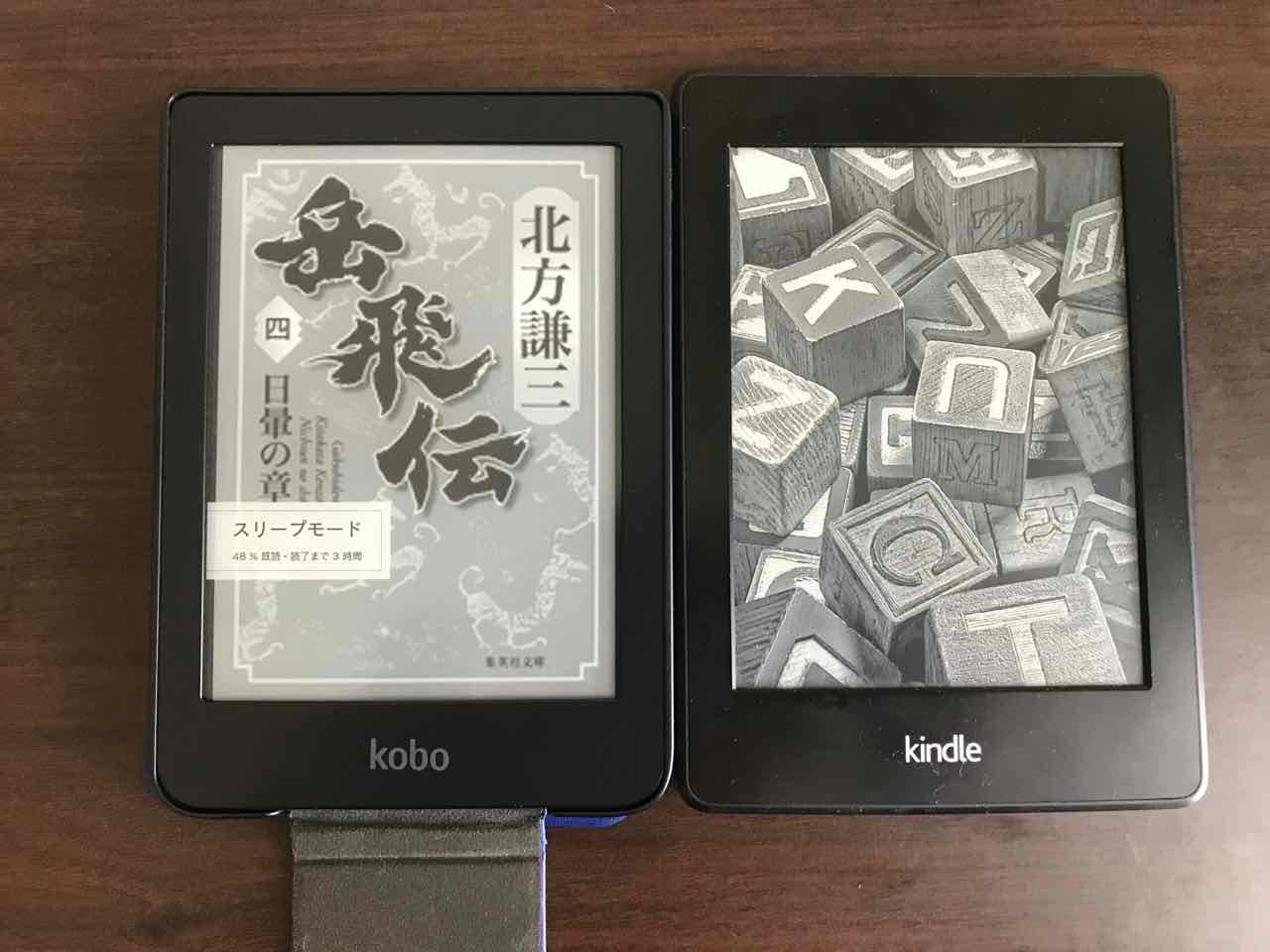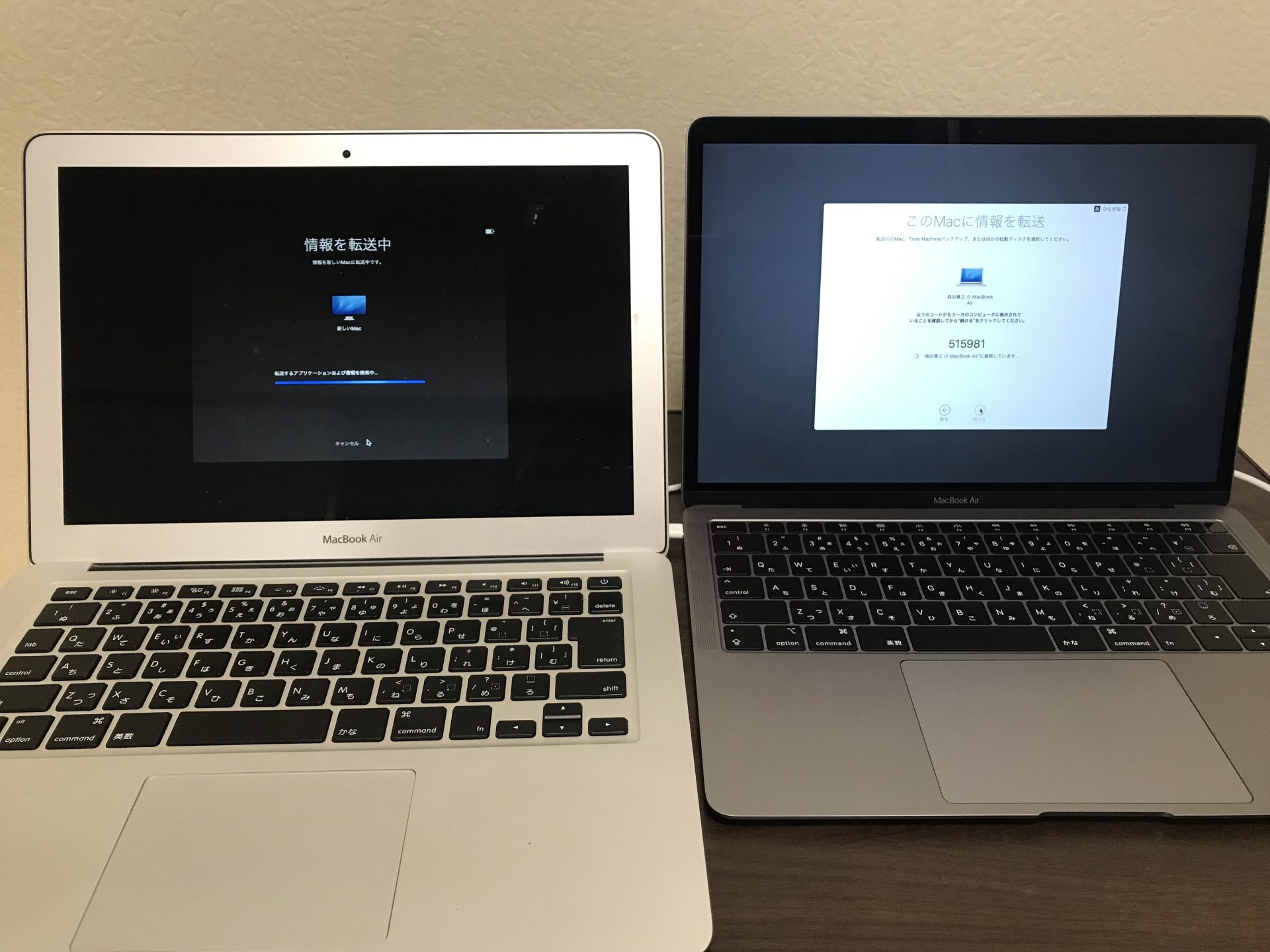田舎で一人暮らししていた母の他界に伴い、田舎の家と田畑を相続することになりました。東京に生活基盤がある身としては、正直取扱いに悩んでいます。ただ田舎暮らしはセカンドライフの選択肢の一つでもあります。農業も趣味にすることもありかなと。私同様、田舎の家の相続で悩む人も多いでしょうから、「二拠点生活・田舎暮らし」のカテゴリーで記録を残していきます。
田舎の田畑の基本情報(スペック)
私の田舎は長野県の安曇野市。観光地として少しは有名かもしれません。その安曇野でもさらに田舎のほうに、家と田畑はあります。東京の家からの移動時間は4〜5時間。正直帰れて月に1〜2回くらい。
所有数は田が2枚に、畑が9枚です。売っても大してお金にはならないだろうと思われます。また同列の相続人である私の兄弟(こちらも田舎からでて都会暮らし)の同意も得られないことから、当面は田畑は私が所有の方針です。
方針1 人に貸す
2枚の田と6枚の畑は、親の代から人に貸していたので引き続きお願いすることにしました。田は兄弟が食べられる分のお米を現物で納めてもらうことで、小作料はなし。
畑は利益がでないようなので、0円で使ってもらう予定です。
休耕地にするよりはマシという判断です。
方針2 自分で畑をやる
畑3枚のうち、1つは親が耕していたので、畑として使いものになります。ネギが少し植えられていた程度でいろいろ植えるキャパはあります。とりあえずジャガイモを少し植えてみました。シカが畑を荒らしてしまう場所のなので、植えたジャガイモ、食べられててしまうかもしれません。限られた帰省回数で何が育つか、試行錯誤をしていきます。

方針3 休耕地を復活させる
残りの2枚の畑は農耕機が入らない不便な場所で、休耕地となっていました。なんと人の背よりも高い松が何本も畑の中に生えていたりする荒れよう。

周りの畑に迷惑をかけてる気もしたので、このゴールデンウィークに少し手をいれました。松を枝や幹をノコギリやナタで切って、根を掘り起こして引き抜きます。写真のクラスで畑に根をはやしている松が何本も。すべて手作業で結構な重労働。気分は開拓民です。

抜いた松でこれだけの山ができます。

なんとか畑が見通せるようになりました。

畑として使えるようになるもは程遠いですが、最初の一歩。この畑をどのようにしていったら資産価値がでるのか、1年かけて考えます。